更新日
50歳から住宅ローンを組む場合の注意点は?
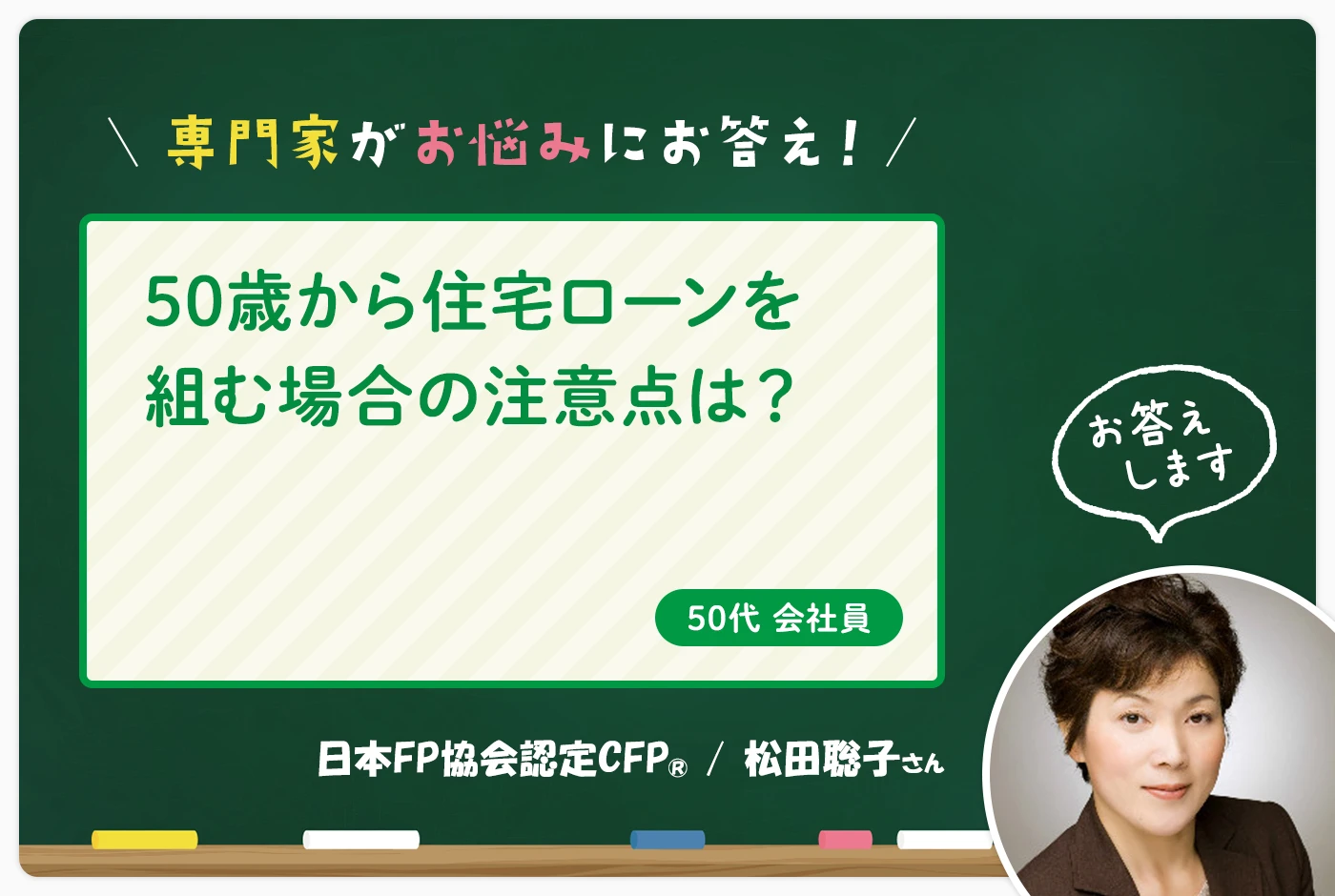
ご質問内容
50歳で夫婦共働きの男性会社員です。
子育てが終わり、これから夫婦二人で住む家の購入を考えています。しかし、住宅ローンを無理なく返済していけるか不安です。
自己資金は1,000万円で3,000万円程度の物件を買うつもりです。2,000万円の住宅ローンを15年で返済する計画ですが、何か注意点はありますか。
年齢:50歳
職業:会社員
世帯年収:800万円
専門家の回答
50代でも収入の安定している方であれば、老後資金準備をしながらの住宅ローン返済は可能です。安心してマイホームを購入するために、ご相談者様の状況を踏まえた注意点を挙げさせていただきます。
●金利・金利タイプ
まず、2,000万円の住宅ローンを15年で返済する場合の、毎月の返済額を試算してみます(元利均等返済、ボーナス返済なし)。金利は年率0.5%から2.0%で見ていきましょう。
- 金利0.5%:115,352 円
- 金利1.0%:119,698 円
- 金利1.5%:124,148 円
- 金利2.0%:128,701 円
金利2.0%の場合で月あたり約13万円(年額156万円)の返済となり、世帯年収800万円に対する返済負担率(収入に占める年間の返済額の割合)は19.5%となります。また、手取り年収を額面の80%の640万円として返済負担率を求めると、約24.3%です。返済負担率は25%以下が望ましいとされており、相談者様のケースでは手取りベースでも25%を下回っていることから、無理のない返済と考えられます。
ここで注意が必要なのが、金利タイプの選択です。住宅金融支援機構の「住宅ローン利用者の実態調査(2024年4月)」によると、2023年10月から2024年3月までに住宅ローンの借り入れをした人のうち、変動金利を選んだ人の割合は76.9%でした。現在の変動金利では年率0.5%以下で借りられる金融機関も多く、低金利が人気の要因といえるでしょう。
しかし、2024年3月に日銀はマイナス金利政策を解除し、利上げに踏み切りました。2024年8月までのところ、変動金利、固定金利ともに各金融機関の金利動向に大きな変動はありません。ただし、全期間固定金利のフラット35の金利は、2021年から上昇傾向にあります。また、変動金利の基準である短期プライムレートの引き上げを発表したメガバンクもあり、今の水準の変動金利は続かないと考えたほうがよいでしょう。
ご相談者様の場合、返済負担率からもある程度の金利上昇には耐えられると考えられるため、金利タイプは変動金利、固定金利のどちらを選んでも大きな問題はないといえます。変動金利を選んだ場合は金利上昇に備え、余裕資金を繰り上げ返済に回せるように準備しておくとよいでしょう。
また、今後の金利動向を注視するようにしてください。
●団信(団体信用生命保険)
次に、万が一のことがあったときに保険金でローンを完済できる、団信(団体信用生命保険)についてです。
住宅ローンの契約において団信は、民間の金融機関では加入必須、フラット35では任意となっています。しかし、債務者としての立場からも、団信なしでの住宅ローン契約は避けるべきです。健康状態によっては団信に加入できないケースもあるため、持病などがある場合、対策を考えましょう。
金融機関によっては、引受の基準が緩和された「ワイド団信」を取り扱っています。ワイド団信の保障内容は一般の団信と同じですが、多くの場合、金利が0.3%程度上乗せされます。また、ワイド団信に加入できる年齢は金融機関によって異なり、50歳未満としている場合もある点に注意が必要です。
通常の団信に加入できる健康状態でがんや3大疾病の保障がある団信の利用を考えている場合も、年齢制限に注意しましょう。がん団信のような疾病保障付き団信は、加入者の年齢が50歳未満となっている商品がほとんどです。疾病保障付きの団信に入れない場合、一般の団信に加入して、民間の生命保険で疾病の備えするのも1つの方法です。
住宅ローンの審査基準は、金融機関によって異なります。ある金融機関で条件に合わなくても、他社で住宅ローンを検討することも有効な手段です。もし銀行などの金融機関の住宅ローンの審査が不安なら、セゾンファンデックスの住宅ローンもおすすめです。
セゾンファンデックスの住宅ローンは、不動産の担保価値と返済能力を総合的に評価して審査を行います。担保力を重視した審査基準のため、信用情報に不安がある場合や、フラット35の審査に落ちた場合でもご相談可能です。購入する物件以外に、本人か親族が所有する不動産があれば、マンション・店舗・駐車場などでも担保設定ができます。
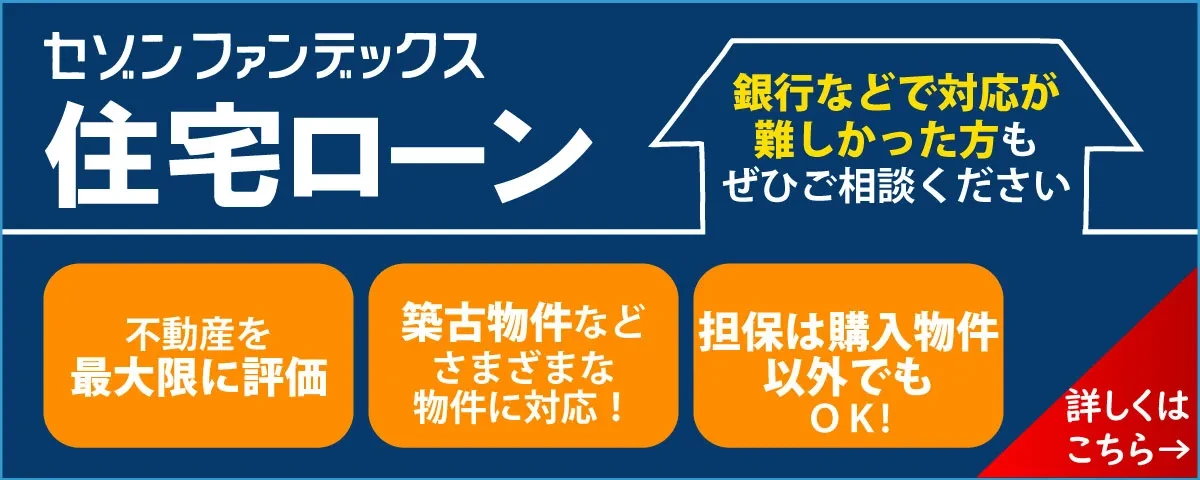
以上、50歳以上で住宅ローンを組む場合の注意点をお伝えしました。ご夫婦で協力して住宅ローンを返済し、経済的に不安のないセカンドライフを迎えられることをお祈りいたします。





